2022年も最終日、12月31日となりました。
この一年の活動の振り返りです。振り返ってみると、今思えば、グループ展、個展、アーティスト・イン・レジデンスをバランスよく行なった一年でした。
狂転体というグループ展で、+1 art、そしてCASで展示を行いました。
不思議な遊びに満ちた展覧会でした。主催の方が楽しんでいたのがとても良かった。長く続ける秘訣だと思いました。
アーティスト・イン・レジデンスには、和歌山、白浜にある川久ホテルにある川久ミュージアム、そして、カナダでは女性のアーティストにフォーカスした施設、MAWAにも参加しましました。
レジデンスでは新たな、アーティストとの出会いがありました。
コロナ禍もあり、新たな出会いが少なくなった中で、このような経験は新鮮で豊かなものでした。
川久のレジデンスでは、二つの大きめの作品制作だったので大変でしたが、家族や友人が手伝ってくれて思い返すと感謝の気持ちでいっぱいになります。
ホテルの方々も、スタッフの方がたも暖かく良い時間を過ごしました。
MAWAでは、海外には3年ぶりで海外に不慣れな感じになってる自分に驚きました。
Project’Doors’の2022年版を制作しました。
MAWAは施設自体が興味深いのと、ウィニペグがアーティストにとって良い市だとも思いました。
MAWAでの滞在を助成を小笠原敏晶記念財団にいただきました。
コロナ禍で、海外のレジデンスに行けることができるのかわからない状況だったので、助成金への応募をしていなかったのですが、
小笠原敏晶記念財団は応募期間の範囲が広く、レジデンス滞在中に応募することができとても助かりました。
今日は、白浜での制作を手伝いに来てくれた人たちと年越しをします。
塩屋の海で朝日を見る予定です。
来年も皆様にとって素晴らしい一年でありますよう!

*散歩した時の塩屋の夕日
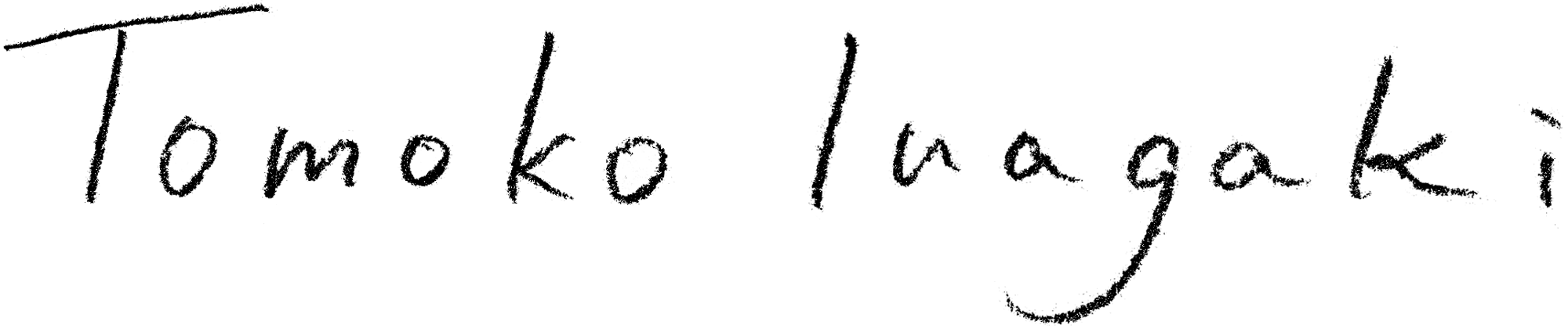

 私は今まで映像やインスタレーション最近始めたを主に作っている。
私は今まで映像やインスタレーション最近始めたを主に作っている。
